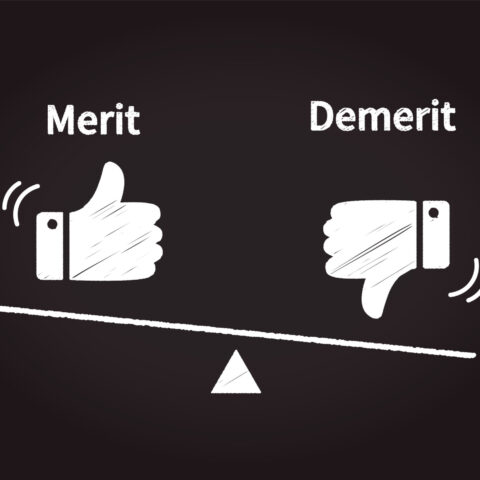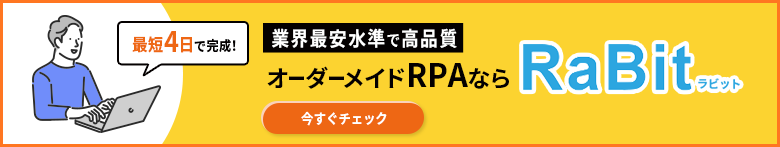近年、業務の効率化を実現するツールとして「RPA(Robotic Process Automation)」のロボットが注目を集めています。繰り返し行う単純作業や定型業務の効率化を実現できるため、より生産性の高い作業に注力しやすくなり、企業の成長力へ貢献できるのもポイントです。
この記事では、RPAのロボットとはなにか、RPAを導入するメリットやデメリットを解説します。デメリットを打ち消すための対策や、RPAのロボットを作成する流れについても解説しますので、あわせてご参照ください。
格安料金ですべてお任せ!「自動化したいこと」をお伝えいただくだけのRPAツール
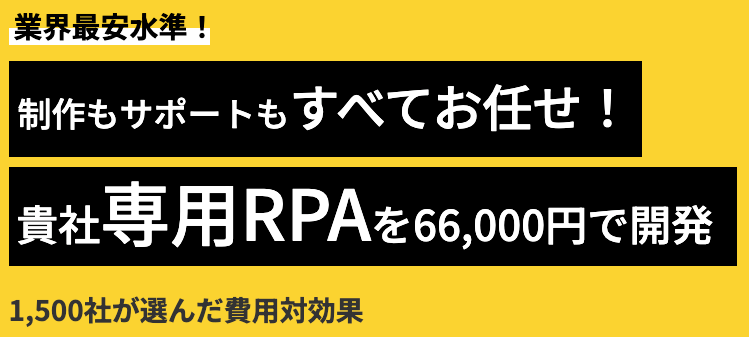
オーダーメイド型RPAツール「RaBit」は、ヒアリング・設計・開発・導入・運用までプロが一気通貫サポート。業界でも格安な料金設定と充実した支援体制で、長く安心してご利用いただけます。
1.RPAとはロボットによる作業自動化のこと

昨今では、「RPA(Robotic Process Automation)」と呼ばれるデスクワークを効率化するシステムが人気を集めています。RPAとは、ロボットを使用して作業を自動化する仕組みで、パソコン上で行う定型業務のほとんどを効率化できるのが特徴です。
ここでは、RPAで自動化できる業務例や、導入が進む背景について解説します。
1-1.RPAで自動化できる業務の例
RPAロボットなら、パソコン上で行う作業手順の定まった業務のほとんどを効率化・自動化できるメリットがあります。具体的な自動化できる業務事例は以下のとおりです。
- 請求書の作成
- 発注リストからシステムへ転記
- 勤怠データの集計や通知
- 競合企業の価格調査
- 受注と在庫の確認業務
- 入金消込作業
- 経費の精算や正誤チェック
- SNS上の口コミ収集
ほかにも、フォームからの問い合わせに対して自動的に返信&内容を業務管理システムへ転記したり、ファイリングしたうえで担当者に自動転送したりする作業も自動化が可能です。複数のシステムをまたいだ処理も自動化できるため、工夫次第でさまざまな定型業務を効率化できます。
基本的に、RPAロボットで自動化できる業務事例のほとんどは、「パソコン上で行う作業手順の定まった定型業務」だと言えるでしょう。
こちらもCHECK
1-2.RPAの導入が進んでいる背景
RPAツールの導入が進んでいる背景に、「人材不足」「長時間労働」「品質の均一化」などがあげられます。特に近年では少子高齢化などの背景から人材不足が進み、業務の処理が遅れた結果、長時間労働を引き起こしている事例も少なくありません。
一方で、RPAは単純ながらも時間の取られる作業や、生産性の低い定型業務を自動化するのに適しているのがポイントです。人材が不足している状態でも業務を効率的に進められるため、長時間労働や残業といった問題を解消しやすい背景があります。
さらに、RPAツールはどのような作業も常に同じクオリティで作業できるため、社員ごとに作業品質を均一化できるのも特徴のひとつ。RPAロボットの活用は多くのメリットがあるため、近年では多くの企業で導入が進められています。
ココがポイント
人材不足が進む昨今において、RPAツールの価値を実感している企業が増えつつある
2.RPAを導入するメリット

RPAのロボットを企業に導入すればさまざまなメリットが得られるため、大企業を始めとして多くのシーンで導入が進められています。特に、単純作業の効率化や作業品質の均一化は大きなメリットです。
ここでは、RPAロボットを導入するメリットをご紹介します。
2-1.生産性が高まる
RPAロボットを導入する何よりのメリットが、生産性を高められる実用性の高さです。RPAのロボットは非生産的な単純作業から、非効率的な業務を効率化する機能性に長けています。
たとえば、Webマーケティング業務をRPA化すれば、「Web上の口コミ等を自動的に収集する」といった情報収集の作業を自動化できます。集計したデータをもとに、各属性へ自動的に振り分けてExcelにまとめる作業も、RPAなら実現が可能です。
Webマーケティング部は自動集計したデータを元により戦略性の高い業務に注力しやすくなるため、コア業務に集中しやすくなるのは大きなメリットです。もちろん、RPAロボットならほかにもさまざまな単純作業を自動化できるため、幅広い業務の生産性を高められます。
ココがポイント
生産性の低い業務を自動化すれば、会社の成長に繋がる業務へ人手を集中させやすくなるのがRPAツールの大きなメリット
2-2.無駄なコストを削減できる
RPAのロボットで業務を自動化すれば、無駄なコストを削減できるのは大きなメリットです。業務のRPA化により一部手順を自動化すれば、「人手のカット」「残業を減らせる」「人件費の削減」などさまざまなコストカットを実現できます。
特に、非生産的な業務を効率化した結果、長時間労働を抑えてコア業務に注力しやすくなるのは大きなメリットです。社内の労働環境を改善できるだけでなく、残業コストなどを削減できます。
加えて、人材はそのままでより生産性の高い業務へ注力しやすくなるため、従来の人件費でより企業の成長力を見込めるようになります。
2-3.ヒューマンエラーが防げる
RPAのロボットは、事前に登録した手順を正確に繰り返すシステムです。人の手で行っているとどうしても起きてしまうヒューマンエラーも、RPAのロボットなら防げます。
そのため、「エクセル同士からデータを転記」「オンプレのシステムにデータを転記」などの基本的な転記作業では、ミスがないかを振り返って確認する手間も掛かりません。
ほかにも、「交通費等の経費申請を正誤チェック」「既存シートとデータの突き合わせ」といった手順や確認方法の定まったミスの確認まで自動化できます。RPAロボットを導入すれば、作業品質の均一化だけでなく、クオリティの向上も実現できると言えるでしょう。
こちらもCHECK
3.RPA導入のデメリットと対策

RPAのロボットは業務の効率化に大きく貢献する一方で、肝心のシステムをうまく活用できなければデメリットが生じてしまうのも事実です。なかには、RPAツールの特性を把握しきれず、導入コストだけがかさんで業務の効率化を実現できなかった事例も少なくありません。
ここでは、RPA導入のデメリットとその対策について解説します。
3-1.ツールによっては使い方を学ぶ必要がある
RPAツールは、ソフトウェアによって異なる使い方が求められる点に注意が必要です。たとえば、RPAツールには直感的に操作できる「マウス&ドラッグ」タイプから、一定のプログラミングスキルが求められるソフトウェアまで多数登場しています。
「RPAのロボットをどのように動かすか」が業務のRPA化に大きく関わるため、使い勝手のよさは業務効率化にも大きく関わってくると言えるでしょう。とはいえ、使い勝手のよいRPAツールを選んだとしても、肝心の業務効率化には「業務の選定」「作業手順の浮き出し」などさまざまな作業が求められるのも事実です。
RPAのロボットをうまく稼働させる自信がない場合は、対策としてサポート力に優れたRPAベンダーを選ぶのがベストです。たとえば、RPAツールベンダーのRaBitでは、要件定義・設計・開発・導入までプロが一括サポートするほか、運用中のトラブルに対するサポートも充実しています。
3-2.システムエラーで業務に支障が出る場合がある
RPAのロボットはヒューマンエラーの抑止に役立つ一方で、万が一のシステムエラーが起きてしまうと、自動化した業務が一括でストップしてしまうデメリットがあります。
また、RPAのロボットは事前に登録した作業手順に沿って同じ動作を繰り返すため、使用しているシステムのUIがアップデートで変更されてしまうと、意図しない動作で業務に支障をきたすおそれも。
RPAのロボットは業務の効率化を実現するのに大きく貢献します。しかし、完全に任せきりになってしまうと業務のブラックボックス化や、万が一の業務ストップなど大きなリスクがあるのも事実です。
対策としては、「RPA化した業務も人力対応できるようマニュアル化する」「システムエラーが発生したらスピーディに対応できる体制を整える」「迅速にサポートしてくれるRPAベンダーを選ぶ」などがあげられます。
ココがポイント
RPAツールは一度自動化した作業も、手順内容に変更がないか定期的な確認・メンテナンスが求められる
3-3.現場でうまく活用されない場合がある
RPAのロボットは業務の効率化に大きく貢献する一方で、トップダウン方式で強引に導入してしまうと、現場でうまく活用されない可能性があります。よくある活用の失敗事例では、「RPAのロボットが作業をすることに不信感がある」「そもそも有効活用する手法がわからない」などです。
対策としては、「RPAロボットを導入する目的の周知」「小さい部署で自動化した事例を共有する」「現場の状況に見合った機能のツールを導入」などがあげられます。まずは一部業務を自動化するスモールスタートからはじめて、実際にどのような効果を得られるのか実例を添えると現場担当者の理解を得やすくなります。
RPAロボットを有効活用して業務を効率化するには、現場単位での協力が必要不可欠です。RPAを推進する担当者を決めて、現場からの質問に対応したり、導入や運用をサポートしたりできる環境を整えると現場単位での導入が進みやすくなります。
こちらもCHECK
4.RPAのロボット(シナリオ)を作成する流れ
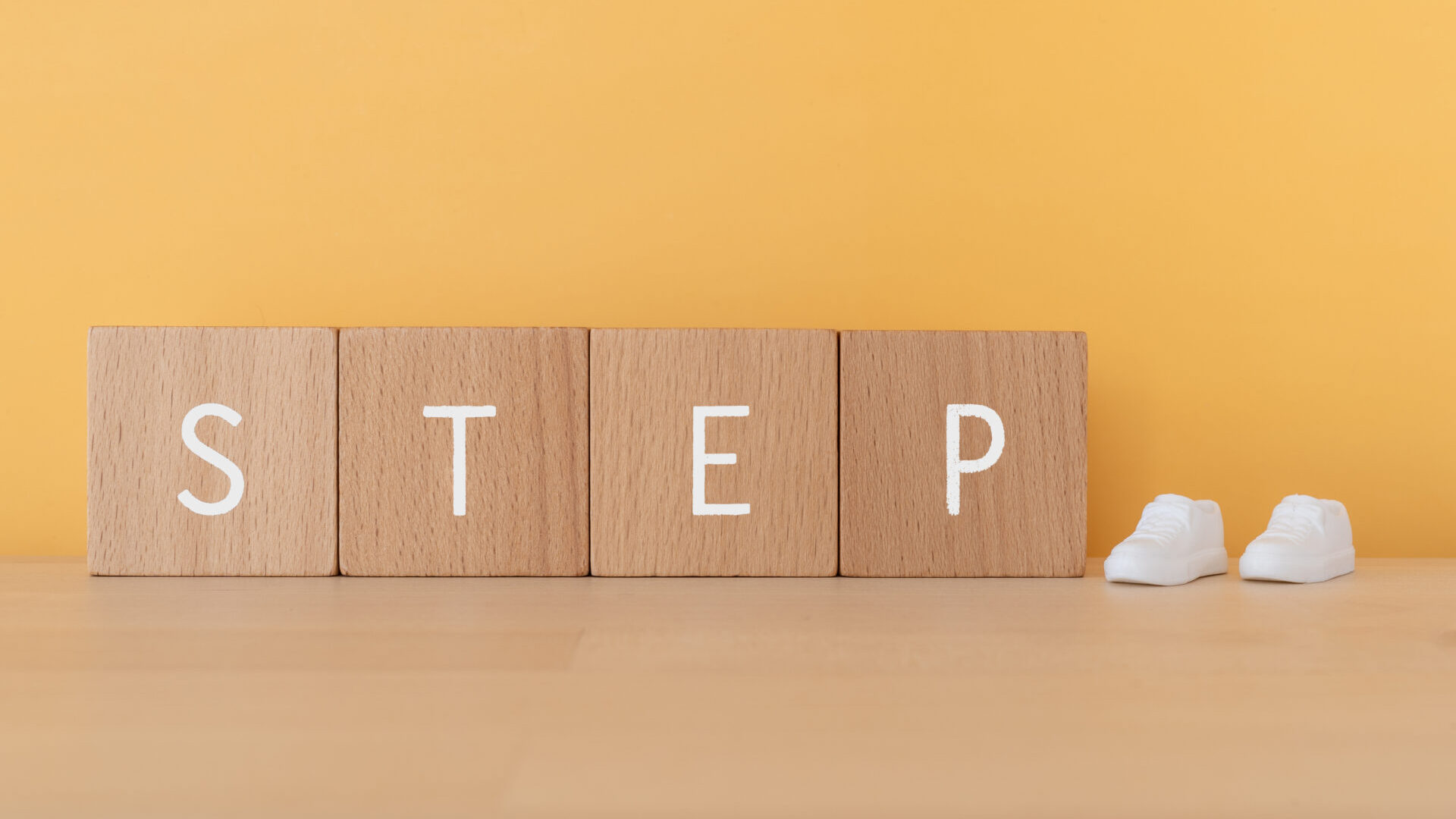
RPAのロボットには、シナリオと呼ばれる業務の手順書を登録する作業が存在します。シナリオの作成はRPAロボットの肝とも言える重要な作業です。そのため、適切なシナリオの作成手順を把握してから、RPAロボットを導入するのをおすすめします。
ここでは、RPAのロボット(シナリオ)を作成する流れを解説します。
4-1.自動化する対象業務を洗い出す
はじめに、RPAのロボット(シナリオ)を作成する準備段階として、自動化する対象業務を洗い出す必要があります。RPAツールはパソコン上の定型業務をほとんど自動化できる一方で、その都度判断が求められるような作業を自動化するのは難しくなっています。
「RPAツールを導入したら思っていた業務を自動化できなかった」といったトラブルを避けるためにも、業務を自動化できるかどうかのチェックは重要です。また、業務を洗い出す過程で不要だった手順や効率化できるポイントが見つかる事例も存在します。
なお、自動化する対象業務を洗い出すときは、小規模の業務をRPA化するスモールスタートを念頭に置きましょう。いきなり多くの業務をRPAのロボットで自動化しようとすると、大きなシステムトラブルや業務停止などの問題を招いてしまう可能性もあります。
4-2.RPAツールの管理画面でロボットを作成する
対象業務を洗い出せたら、RPAツールの管理画面で実際にロボットを作成します。具体的な設定方法は活用するソフトウェアによって異なるものの、一度作成したロボットはそのまま業務を設定通り自動的に遂行してくれます。
ロボットの作成では、マウス&ドラッグなどのみで行える簡易型ツールと、プログラミングスキルが求められる開発型ツールなどの2種類が存在するため要チェックです。RPAツールのなかには「デフォルトの動作」などが用意されており、ロボットの作成手順を簡略化して業務のRPA化を実現しやすいソフトウェアも登場しています。
4-3.必要に応じて調整を加える
RPAロボットの作成が終わったら、必要に応じて調整を加える必要があります。具体的には、「実際にどの程度の業務を効率化できたのか」「ボトルネックになっている作業手順は存在しないか」「業務効率化の費用対効果チェック」などがあげられます。
また、RPAのロボットは事前に登録した手順をつねに繰り返す仕組みのため、作業手順のシステムにUI変更などがある場合は、適宜修正しなければなりません。ツールによってはある程度の補正はできるものの、UIの変更などを見落としていると業務が意図せぬ場所でストップしてしまうため、適宜調整を加える作業が必要不可欠です。
こちらもCHECK
5.オーダーメイドRPA制作サービス「RaBit」ならロボット作成の手間が不要
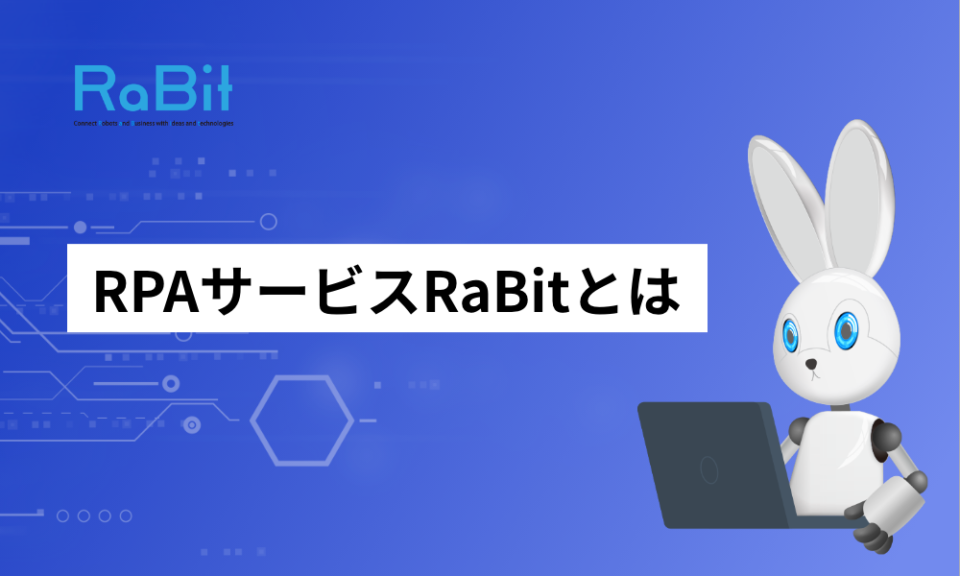
「手間をかけずにRPAのロボットを自社に導入したい」とお考えのときは、ぜひオーダーメイドRPA制作サービス「RaBit」をご利用ください。
RaBitではヒアリングから要件定義、設計、開発、導入、運用サポートまで行っており、お客様は「自動化したい作業」をお伝えしていただくだけでRPAのロボットを導入できるメリットがあります。
さらに、業界のなかでも圧倒的なコストパフォーマンスを誇る価格の安さも魅力のひとつ。初期費用は66,000円から、月々10,450円からご利用いただけるため、低コストでRPAのロボットを導入しやすいのもポイントです。
専門家の導入・運用サポートだけでなく、トラブルもスピーディに対応できるサポート体制を整えておりますので、「RPAロボットを手軽に導入したい」とお考えの方はぜひお気軽に「RaBit」までご相談ください。
6.まとめ

RPAのロボットは、大企業を始めとして中小企業でも広く導入が進められています。業務の効率化に大きく貢献できるだけでなく、単純作業を減らすことで、残業の削減や長時間労働環境の改善など、社員にとっても大きな魅力が存在します。
一方で、RPAのロボットを導入するには、実用的な業務効率化を実現するために一定のスキルが求められるのも事実です。なかにはマウスのドラッグ&ドロップだけで業務を自動化できるツールも登場しているものの、実際には「業務の洗い出し」「現場単位で導入を浸透させる」「導入前後の効果検証」などさまざまな敷居が存在しています。
もし、RPAのロボットをお手軽に導入したいとお考えの場合は、ぜひお気軽にオーダーメイドRPA制作サービス「RaBit」までご相談ください。「RaBit」なら専門家が要件定義、設計、開発、導入、運用サポートまで行っており、お客様は「自動化したい作業」をお伝えいただくのみとなります。
RPAロボットによる業務効率化の効果をスピーディに実感したい方は、ぜひお気軽に「RaBit」までご相談ください。